トップページ > 会社を強くする基礎知識 > 労務トラブル解決 > 解雇に関するトラブル
2018.6.1
解雇に関するトラブル
【労務トラブル解決】

退職トラブルの中で、よく相談を受けるのが従業員を解雇したことによるトラブルです。
経営者であれば、勤務態度の悪い従業員や協調性のない従業員を、一度は解雇したいと思ったことがあるのではないでしょうか。
経営状況が思わしくなく、パートやアルバイトの雇い止めや人員整理に踏み切らざるを得ないこともあったかもしれません。
一般の商取引のように、契約解除をできればよいのですが、労働契約の場合、そういうわけにはいきません。
労働契約法第16条には、次のように定められています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
簡単に言うと、会社が、従業員を解雇するには、誰しもがうなずけるような理由がないといけない(=無効)、ということです。
従業員にも生活がありますから、一方的な解雇には、納得できないこともあるでしょう。
本人のみならず、ご家族が納得していないケースも、充分に考えられます。
こういった時に、会社に対し、解雇無効として主張されてきます。
通常、従業員が個人的に会社に対して訴えを起こすには、法的知識が不足していることが多いため、以下のような“第三者”を介してきます。
(労働基準監督署)
労働基準監督署では解雇の有効性は判断できない為、労働局のあっせんやADR制度を進められるケースがほとんどです。
あっせん制度ではあっせん委員が中立の立場に立って和解協議する事になります。
(労働組合)
従業員が、外部の組合に加入するケースと社内で労働組合を結成するケースがありますが、前者である場合がほとんどです。
外部の労働組合は、経験豊富で労使交渉に長けています。
正論が通用しない事も多く、弁護士よりも強力な時もあります。
(弁護士)
本人に代わって、会社との交渉窓口になります。
依頼者(=元従業員)の正当な利益を実現する義務が、法律により課せられています。
この“第三者”に対抗するには、会社としても、法的知識武装をしなくてはならず、多くの時間と労力を費やしてしまうことになります。
会社を強くする基礎知識「労務トラブル解決編」
-
2018/6/1
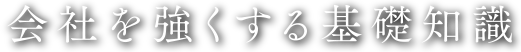

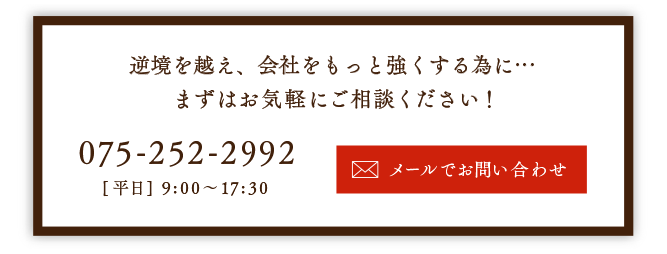
![お問い合わせ 075-252-2982[平日] 9:00~17:30](https://www.kyoto-forest.net/img/common/p_side1.png)

